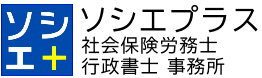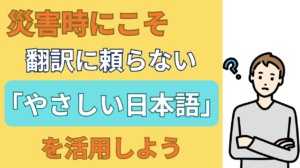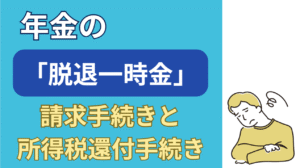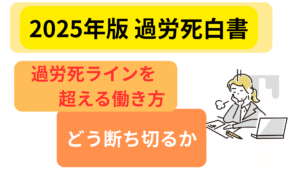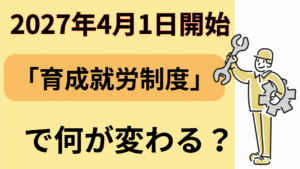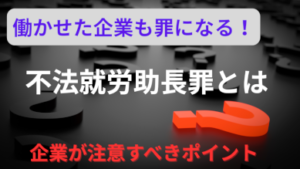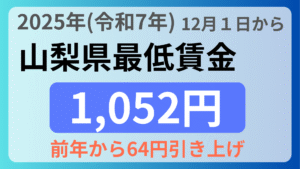特定技能「ベトナム一強」に陰り。次なる主役はインドネシア・ミャンマーか
記事の要点
日本の人手不足を支える「特定技能」の在留資格を持つ外国人の国籍構成に、大きな地殻変動が起きています。出入国在留管理庁の最新データ(2025年6月末時点)によると、これまで圧倒的多数を占めていたベトナムの比率が44.2%と、前年同月末の50.4%から縮小しました 。
総数ではベトナムが約15万人と、2位インドネシア(7万人)、3位ミャンマー(3万6千人)を依然引き離しています 。しかし、この1年間の「増加数」を見ると、インドネシアがベトナムを抜き去り、ミャンマーも前年(2024年)の増加数(約1万8千人)から、2025年にはベトナム(約2万人)に迫る約1万5千人の増加を見せています 。製造業や介護を担う人材の供給源が、明らかに転換しつつあるのです 。
特定技能と技能実習の違い
ここで、混同されがちな「特定技能」と「技能実習」の違いに触れておきます。
- 技能実習: 目的は「国際貢献」としての技術移転です。原則として転職は認められず、家族の帯同もできません。
- 特定技能: 目的は明確な「労働力の確保」です。同一分野内での転職が可能であり、2号資格になれば家族帯同も認められます。
「転職が可能」である特定技能において、今回の国籍動向の変化は、企業にとってより切実な問題となります。
考察:なぜベトナムが減速し、他国が伸びるのか
背景には、円安の進行や、自国の経済成長といった、日本の魅力の低下かがあります。母国への仕送りを目的とする労働者にとって、手取り額が目減りする日本は「稼げない国」になりつつあります。特にベトナムでは、来日前の高額な手数料負担も問題視されており、魅力が相対的に低下しています。
一方で、インドネシアはもともと親日的な国民性に加え、家族のために働くという強い動機があります。また、ミャンマーは2021年のクーデター以降の国内情勢不安 や、日本とミャンマー語の文法の類似性(学習のしやすさ)、二国間協定によるスムーズな送り出し体制 が、日本への人材流入を後押ししていると考えられます。
注意点:一国依存の経営リスク
今回の動向は、特定の一国に人材確保を依存する経営リスクを浮き彫りにしました。企業が注意すべき点は以下の通りです。
- 為替・経済リスク: 円安のように、自社でコントロールできない外部要因で、魅力的な労働市場でなくなるリスク。
- カントリーリスク: 送り出し国の政治情勢(ミャンマーなど)や政策変更により、人材供給が突如ストップするリスク。
- 獲得競争の激化: ベトナムからの人材確保が難化する中、今後はインドネシアやミャンマーの人材獲得競争が激化し、採用コストが高騰する可能性があります。
解決策:供給源の多角化と「選ばれる」職場づくり
この変化に対し、企業は以下の対策を講じるべきです。
- 採用チャネルの多角化: ベトナム一辺倒から脱却し、インドネシア、ミャンマー、フィリピン など、複数の国からの採用ルートを確立します。
- 定着支援の強化: 「特定技能」は転職が可能です。採用後の日本語教育の継続、キャリアパスの明示、良好な職場環境の整備など、「定着」してもらうための努力が不可欠です。
- 「円安」以外の魅力向上: 給与(円)の価値が低下している以上、金銭以外の魅力を高める必要があります。文化的な配慮、明確な評価制度、住環境のサポートなど、総合的な「働きやすさ」で選ばれる企業を目指すべきです。
まとめ:労働力から「パートナー」へ。意識改革のとき
特定技能人材の供給源の変化は、日本がもはや自動的に「選ばれる国」ではないという厳しい現実を突きつけています。
企業は、外国人を単なる「労働力」として見るのではなく、共に働く「パートナー」として迎え入れる意識改革が求められます。目先の採用活動に一喜一憂するのではなく、人材の供給源を多角化し、一度縁を持った人材が長く働きたいと思える環境を整備すること。それこそが、不安定な時代を乗り越えるための中長期的な人材戦略の鍵となるでしょう。