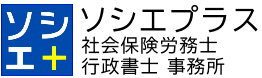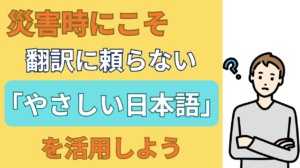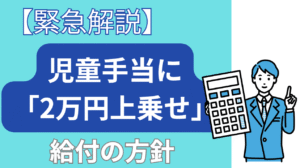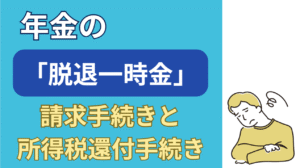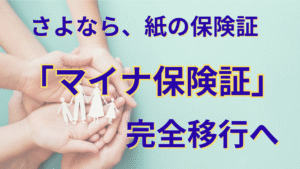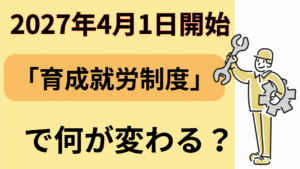【令和7年版 過労死白書】過労死ラインを超える働き方をどう断ち切るか
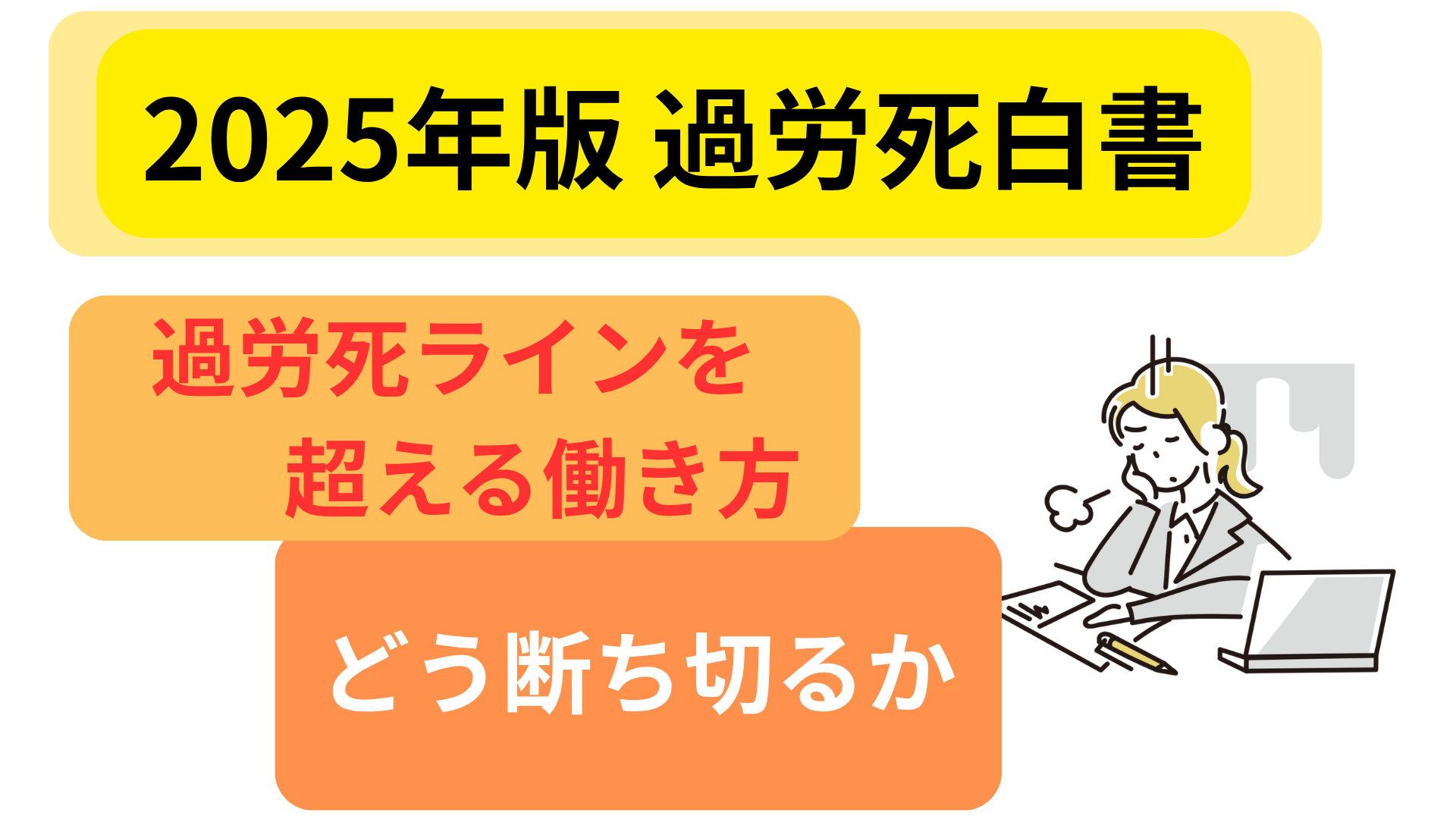
【令和7年版 過労死白書】運輸・宿泊・教育で依然深刻な「週60時間超」の現実。過労死ラインを超える働き方をどう断ち切るか
記事の要点
厚生労働省がこのほど公表した「令和7年版 過労死等防止対策白書」は、日本の労働環境の「光と影」を改めて浮き彫りにしました。
全体の傾向として、週の労働時間が60時間を超える雇用者の割合は8.0%と、前年(8.4%)から0.4ポイント減少し、長期的な減少傾向が続いています。これは、働き方改革関連法による時間外労働の上限規制が一定の成果を上げていることを示唆しています。
しかし、その内訳に目を向けると、深刻な実態が浮かび上がります。業種別で「週60時間以上」の割合が最も高かったのは「運輸業, 郵便業」で17.7% 。次いで「学術研究, 専門・技術サービス業」(15.1%)、「教育, 学習支援業」(13.9%)、「宿泊業, 飲食サービス業」(11.7%)と、特定の業種に極端な長時間労働が集中している実態が明らかになりました。
考察
なぜ、これらの業種で長時間労働が解消されないのでしょうか。背景には、慢性的な人手不足、24時間稼働や対人サービスといった業務の特性、そして旧態依然とした商慣行といった、根深い構造的問題が存在します。
特に懸念されるのが、精神障害による労災認定の増加です。白書によれば、精神障害の労災支給決定件数は令和6年度に1,055件と過去最高を更新。その要因として、「対人関係」や「パワーハラスメント」が近年急増しています。長時間労働による疲弊が職場のコミュニケーションを阻害し、ハラスメントの温床となっている可能性は否定できません。
例えば、「教育, 学習支援業」では精神障害の要因として「上司とのトラブル」や「パワーハラスメント」の割合が他業種より高く、一方で「自動車運転従事者(運輸業)」や「外食産業」では「1か月に80時間以上の時間外労働」が直接的な要因となるケースが多いなど、業種特有のリスクが明確になっています。
令和6年4月からは、これまで猶予されていた運輸業や建設業、医師にも時間外労働の上限規制が適用されました 。しかし、規制強化だけでは問題は解決しません。人手不足という根本原因に対処しなければ、現場の負担は変わらず、違法なサービス残業が横行する事態も懸念されます。
注意点
企業がこの状況を放置すれば、極めて重大なリスクを負うことになります。
- 法的・経営的リスク: 労働基準法違反による罰則はもとより、過労死や精神疾患が発生すれば、安全配慮義務違反として民事訴訟に発展し、多額の損害賠償を命じられる可能性があります。また、違法な長時間労働が明らかになれば企業名が公表され、「ブラック企業」としての社会的信用の失墜は免れません。
- 人材流出の悪循環: 長時間労働が常態化する職場では、当然ながら従業員の満足度は低下します。結果、優秀な人材が流出し、残された従業員の負担がさらに増大。人手不足が加速し、企業競争力そのものが失われるという負のスパイラルに陥ります。
働く個人にとっても、週60時間を超える労働は「過労死ライン」に直結する危険な状態です。白書の調査でも、週60時間以上働く人の61.7%が睡眠で十分な休養が取れていないと回答しています。
解決策
この負の連鎖を断ち切るため、労使双方が今すぐ取り組むべき対策があります。
企業側:
- 勤務間インターバル制度の導入: 終業から次の始業まで最低限の休息時間(例:11時間)を確保する制度です。導入企業はまだ5.7%に過ぎませんが、労働者の健康確保に極めて有効です。
- ハラスメント対策の徹底: 精神障害の最大の要因となりつつある「対人関係」の問題に対処するため、相談窓口の実効性を高め、管理職への研修を義務化するなど、ハラスメントを許さない職場風土を本気で構築する必要があります。
- ICT・AIの積極活用: 白書でもHITO病院の事例が紹介されているように、チャットツールの導入で医師との連絡待ち時間を削減したり、AIを活用して事務作業を自動化するなど、テクノロジーで業務効率化を図ることは不可欠です。
労働者側:
- 「休む権利」の行使: 年次有給休暇の取得率は改善傾向にありますが、ためらわずに休暇を取得し、心身をリフレッシュさせることが重要です。
- 外部窓口への相談: 職場の環境改善が見込めない場合や、心身に不調を感じた場合は、決して一人で抱え込まず、「こころの耳」や「労働条件相談ほっとライン」といった公的な相談窓口を活用してください。
まとめ
今回の過労死白書は、日本の「働き方」が業種によって二極化している厳しい現実を突きつけました。運輸、宿泊・飲食、教育といった社会インフラを支える現場の疲弊は、もはやその業界だけの問題ではなく、社会全体の持続可能性を脅かす問題です。
経営者は「人手不足だから」という言葉を免罪符にせず、今こそ本気で職場環境の改善と業務効率化に投資し、「選ばれる職場」への変革を断行しなければなりません。
そして働く私たち一人ひとりも、長時間労働を「美徳」や「仕方ないこと」と捉える意識を変革し、健康に働く権利を主張していく必要があります。
「命より大切な仕事はない」――この原点に立ち返り、社会全体で過労死ゼロを目指す覚悟が問われています。