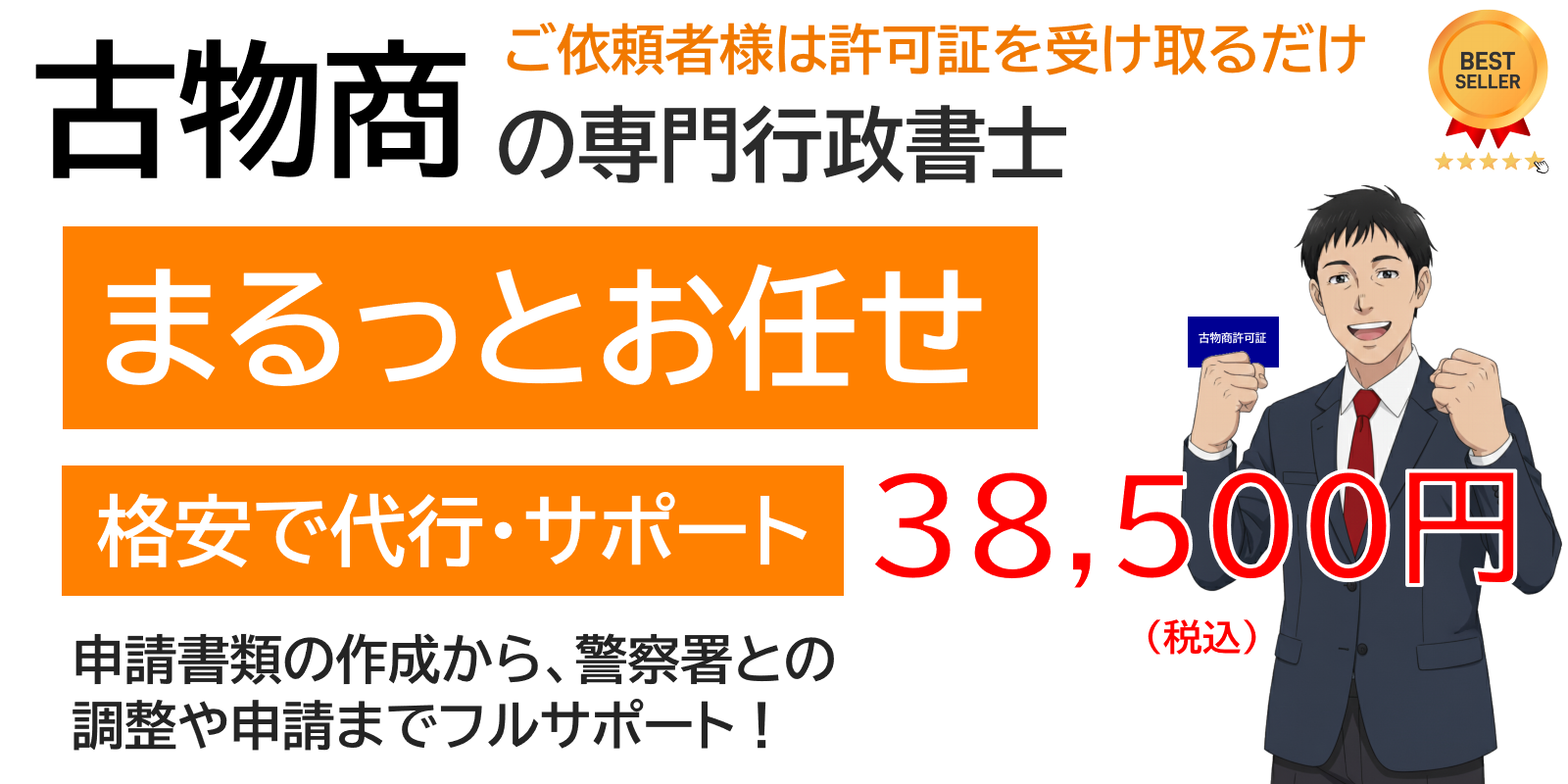_
_
古物商許可申請を行政書士が「まるごとサポート」
古物商許可申請をお考えの皆様さま、
こんなお悩みはありませんか?

- 古物商の許可を取りかたを調べるのが面倒!
- 仕事が忙しいくて、許可手続きを代行してほしい!
- 警察署に行くことが苦手で、提出だけお願いしたい!
- 許可を取得するまでどれくらい時間が掛かるの?
- メルカリやフリマも古物商の許可が必要なの?
- ネットを使って中古品売買のホームページを開設する予定だけど・・・
- 古物商を開業後も気軽に問合わせたい!
※許可取得が少しでも負担・ストレスに感じる場合は
専門家に丸投げ願います。
まずは相談から。相談は初回無料です。
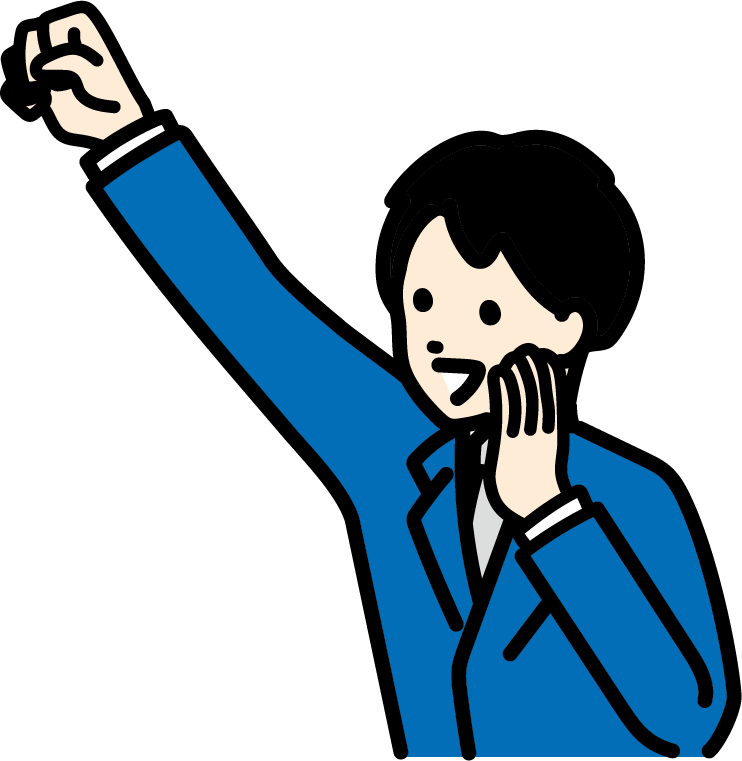 選ばれる5つの理由
選ばれる5つの理由

全部まかせて低コスト
でも安心のサポート!
他事務所の申請代行の平均相場は7万円ほどですが、当事務所は ①まるごとお任せプランが38,500円、②スタンダードプランが25,850円という地域最安水準。専門特化だから実現できるベストプライス、サポート内容もに不足はありません
→ 料金表はこちら

24時間オンラインで完結
まるっとお任せ!
当事務所は、お客様とのやり取りのオンライン完結を目指しており、打ち合わせはメールやLINEを使用して行います。最短5分!ヒアリングシートに入力するだけで、初回お問合せが完了します。
→ お問合せはこちら

日本全国 どこでも対応!
本業で忙しい方におすすめ
相談は、お問合せフォームからご予約をいただければ対応可能です。その方法も対面やオンライン(Googlemeetを利用 ※Googleアカウントがなくても大丈夫です。)が可能です。お気軽にお問い合わせください → お問合せはこちら

ご自分にぴったりのプランが
選択できる!
弊所は選べる2つのプランをご用意しており、それぞれオプションもご用意しております。
ご自分に合ったプランにオプションをつけることで、ご自分に最適な形でのご依頼が可能となっています。
→ まるごとお任せプランの流れはこちら

専門の行政書士だからこその安心感!
開業後も相談できる
古物商の許可の取得を代行できるのは専門識と国家資格を持った行政書士だけです。
警察署の審査実務にも詳しく通じた専門家である行政書士が、全力でサポートします!
事業拡大による法人化や社会保険手続きも相談できます。
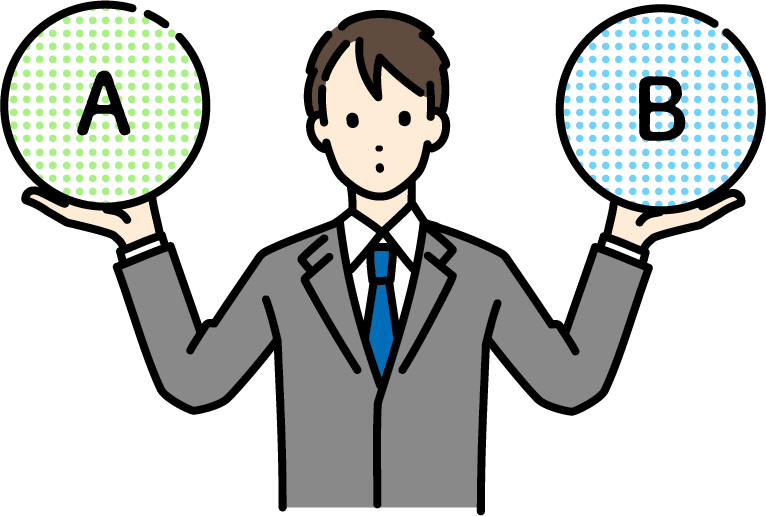 えらべる 2つの料金プラン
えらべる 2つの料金プラン
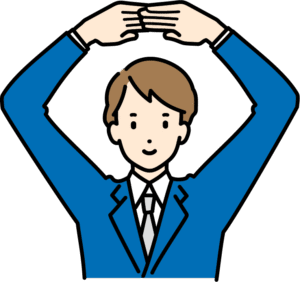
①まるごとお任せプラン
38,500円 税込
- 管轄警察署との協議(当事務所)
- 申請書類の作成 (当事務所)
- 公的書類の取り寄せ(当事務所)
- 警察署への提出代行(当事務所)
- 許可証の受取り連絡(当事務所)
対応エリアは 山梨県内 です。
とにかく忙しい人はこのプランがおすすめ
自分のビジネスに集中したい人向けプランです
お客様は許可書の受け取り以外、何もする必要がございません。

②スタンダードプラン
25,300円 税込
- 管轄警察署との協議(当事務所)
- 申請書類の作成 (当事務所)
- 公的書類の取り寄せ(当事務所)
警察署への本人提出(依頼者様)
許可証の受取り連絡(依頼者様)
対応エリアは 全国 です。
書類の作成や取り寄せが苦手な人はこちらのプラン
お客様は警察への書類の提出と許可書の受け取り
及び署名押印をする必要がございます。
※警察署への古物商の許可の申請手数料が別途19,000円必要です。
※法人については各プランに11,000円を加えた額となります。
・役員2人目以降、1人追加につきオプションとして+5,500円必要。
・営業所の管理者が代表者、役員以外の場合、1人につきオプションとして+5,500円必要。
・営業所2ヶ所目以降、1ヶ所追加につきオプションとして+5,500円必要。
※URL追加2件目以降、1件につきオプションとして+2,200円必要。
※臨時株主総会議事録作成、定款変更サポートは+16,500円で承ります。
※オプション費用、委任状のやり取り、住民票や身分証明証などの公的書類の申請手数料と取得に要した実費や郵送料などは別途ご請求させていただきます。
(レターパックライトでやり取りの場合:1通430円、本人限定受取郵便:1通)
※図面作成等特殊な業務が発生する場合は別途お見積りとなります。
_
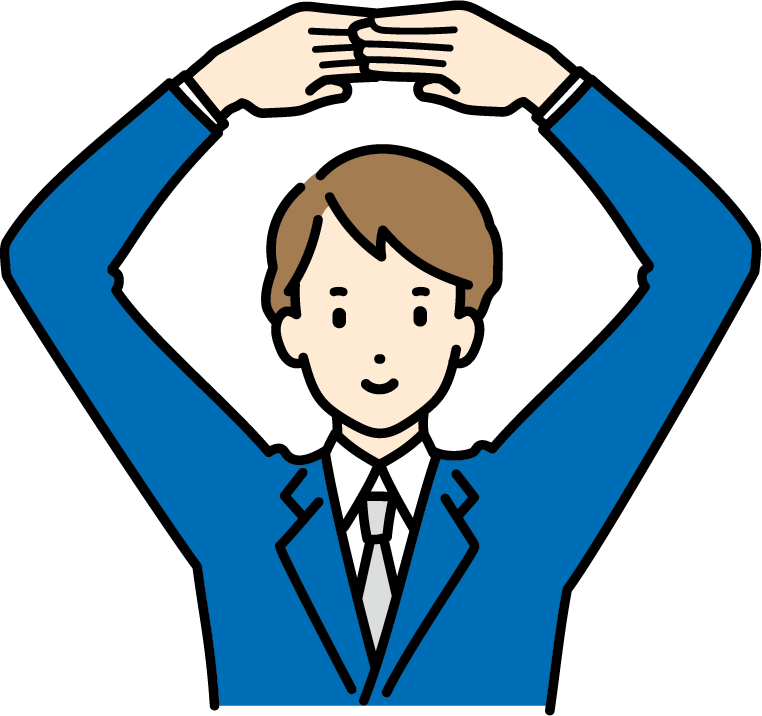 まるごとお任せプランの流れ
まるごとお任せプランの流れ
38,500円(税込) ※法人は11,000円加算
お問い合せ内容に「古物商許可申し込み」と入力の上、「送信する」をクリック!
(ご依頼者様)
(当事務所)
(ご依頼者様)
(当事務所)
(ご依頼者様)
(当事務所)
(ご依頼者様)
(当事務所)
(当事務所)
(当事務所)
(当事務所) _
※スタンダードプランではご依頼者様が提出
※警察署への申請料金「19,000円」が別途必要です。
(当事務所)
※スタンダードプランではご依頼者様に直接連絡
(当事務所)
※警察による現地確認がある場合は申請者様にてご対応いただきます。
※許可証の交付まで申請提出から約40日程度となっております。
| お見積りのご依頼から、警察署への申請書提出まで、通常 2週間から1ヶ月程度かかります。 |
| 申請から許可証の交付まで約40日程度かかります。 ※お見積り依頼から1.5~2か月は事業が開始できません。 お早めに準備を! |
_
 スタンダードプランの流れ
スタンダードプランの流れ
25,300円(税込) ※法人は11,000円加算
お問い合せ内容に「古物商許可申し込み」と入力の上、「送信する」をクリック!
(ご依頼者様)
(当事務所)
(ご依頼者様)
(当事業所)
(ご依頼者様)
(当事務所)
(ご依頼者様)
(当事務所)
(当事務所)
(当事務所)
(当事務所)
(ご依頼者様)
※まるごとお任せプランでは当事務所が提出を代行します。
※警察署への申請料金「19,000円」が別途必要です。
(ご依頼者様)
※警察による現地確認がある場合は申請者様にてご対応いただきます。
※許可証の交付まで申請提出から約40日程度となっております。
許可がおりましたら警察から連絡があります。
| お見積りのご依頼から、警察署への申請書提出まで、通常 2週間から1ヶ月程度かかります。 |
| 申請から許可証の交付まで約40日程度かかります。 ※お見積り依頼から1.5~2か月は事業が開始できません。 お早めに準備を! |
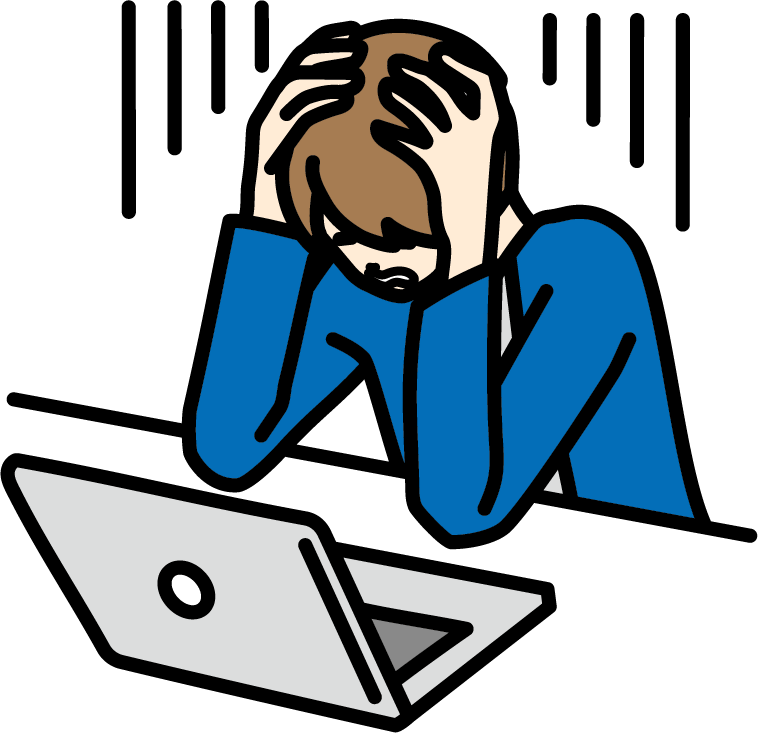 古物商の許可がおりません!
古物商の許可がおりません!
古物商許可には「欠格要件」というものがあります。下記に当てはまる場合、許可が下りません。
取得が可能と見込まれる場合は、詳細の打ち合わせおよびご契約に入らせていただきます。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮刑や懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業や名義貸しのほか窃盗、盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団員
- 暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
- 暴力団員以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者
- 暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条(営業の停止等)の規定により古物営業の許可を取消され、その取消しから5年を経過しない者等
- 精神障害により古物営業を適正に営めない者
- 一定の未成年者
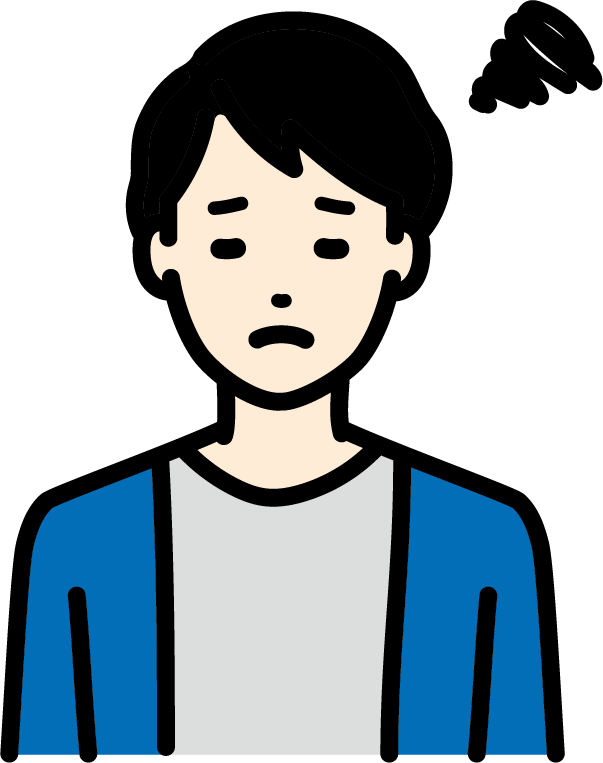 よくある質問
よくある質問
 まるごとお任せプランと、スタンダードプランで迷っています
まるごとお任せプランと、スタンダードプランで迷っています
![]()
まるごとお任せプラントとスタンダードプランの違いは「警察署窓口への申請代行」を含むかどうかです。
まるごとお任せプランは、平日お昼間のお時間が取れない忙しい方や、警察署窓口での質疑対応が不安な方にオススメです。
警察書窓口の質疑応答で、これまでの取引に無許可営業の指摘が入り受理されなかったという相談も多いです。
 なぜ古物の売買に許可が必要なのか?
なぜ古物の売買に許可が必要なのか?
![]()
古物商許可がなぜ必要なのか、かりやすく言うと、「万引きされた商品や盗まれた物の売買・換金を未然に防いだり、すぐに発見できるようにするために、古物の売買には許可制などの規制します。それにより、万引きや犯罪を防止したり、盗品を早く持ち主に返したりできるようにします」ということです。
古物商許可を取らずに営業を行うことは「無許可営業」に該当し、古物営業法の中で最も重い罰則が科されます。(罰則:3年以下の懲役または100万円以下の罰金(併科される場合もあり))
例えば、メルカリShop、リサイクルショップの開業や、中古品の転売(せどり)で許可を取らずに始めてしまう場合が該当します。
古物商許可がなぜ必要なのか、かりやすく言うと、「万引きされた商品や盗まれた物の売買・換金を未然に防いだり、すぐに発見できるようにするために、古物の売買には許可制などの規制します。それにより、万引きや犯罪を防止したり、盗品を早く持ち主に返したりできるようにします」ということです。
古物商許可を取らずに営業を行うことは「無許可営業」に該当し、古物営業法の中で最も重い罰則が科されます。(罰則:3年以下の懲役または100万円以下の罰金(併科される場合もあり))
例えば、メルカリShop、リサイクルショップの開業や、中古品の転売(せどり)で許可を取らずに始めてしまう場合が該当します。
 個人のメルカリ転売に古物商許可はいらない?
個人のメルカリ転売に古物商許可はいらない?
![]()
どこかで「転売目的の古物の買い取り(仕入れ)」を行い、その古物をメルカリで販売する場合は、古物商許可が必要となります。
自分の不用品をメルカリで販売するだけであれば、古物商許可はいりません。
しかし、反復継続してメルカリで古物販売を行う場合、ビジネスとみなされる可能性があり、そのような場合には古物商許可が必要となります。
【古物商に該当するかどうかの判断ポイント】
1.買い取った中古品を転売する
2.買い取った中古品を修繕するなどして販売する
3.買い取った中古品をレンタルする
4.買い取った中古品を分解し、一部分のみを販売する
5.自分以外の第三者から商品を預かり、委託販売を行う(手数料を支払う)
6.国内で買い取った中古品を海外で販売する
7.古物を別のものと交換する
つまり
「転売・レンタルなどの目的で古物の買い取り」を行うかどうかです。
※「未使用品」でも「古物」とされることがあります。
※取引する物品の種類(「古物」の13区分のどれかに該当するかどうか)
 古物商許可が不要な取引は?
古物商許可が不要な取引は?
![]()
・メーカー直売店や卸売店、小売店などから買った「新品」を転売する
・自分のために買った不用品を売る
・無料でもらった物を売る
・処分費用等の手数料をもらって引き取った中古品を売る
・くじやゲームセンターなどで獲得した景品を売る
・自ら海外で仕入れた「古物」を売る(日本国内の輸入代行業者から仕入れる場合には古物商許可が必要です)
・「古物」に該当しないものの取引※1
※1.「古物」に該当しないものの主な例:
・盗難のリスクが低いもの(大きくて重量のあるもの・土地や建造物に固定されているようなもの)
消費してなくなるもの・別の法律で規制されているもの
例:食品・酒・薬品・サプリメント・化粧品
※これらの物品を販売する時には、別の法律に基づく許可が必要な場合があるので、あらかじめ確認しましょう
・本来の性質や用途を変化させたもの(何かをリメイクして別のものに作り変えた場合など)
例:洋服をリメイクしてバッグにしたもの
・形状に本質的な加工をしないと利用できないもの(リサイクルして原材料になるようなもの)
例:空き缶類・鉄くず・繊維くず・古新聞
・再利用できないもの
例:一般ごみなどの廃棄物
・投機目的の貴金属など
例:インゴット(加工前の貴金属)・金塊・金貨・プラチナ
・実体がないもの(オンライン上のものなど、実体がない金券類)
例:電子チケット・オンラインギフト券
 古物商許可が必要なビジネスの具体例は?
古物商許可が必要なビジネスの具体例は?
![]()
古物商の免許を利用したビジネスの形態を具体例を挙げてご紹介させていただきます。
①中古車販売
中古車販売は、古物商で行える仕事の代表例です。
中古車を販売する古物商は許可取得時に他の種目よりも厳しく確認されるます。
具体的には、
・管理人に自動車の専門知識があるかどうか
・自動車を駐車するスペースが営業所にあるかどうか
などが求められます。
自動車の自動車に関する専門知識があるかどうかの目安は「実務経験が3年以上あるかどうか」となっています。
②中古品の買取・販売
古物商許可を利用したビジネスとして最もイメージしやすいのが中古品の買取・販売です。
③リサイクルショップ・質屋・買取業
リサイクルショップは、お客様が持ち込んだ中古品を買い取り、それを店頭やオンラインで販売する店舗です。商品の種類は衣類、家具、家電、玩具など多岐にわたります。
④中古パソコンショップ
中古パソコンの仕入れと転売、ジャンク品の修理後の転売も人気のビジネスです。
パソコン市場は新しいモデルが次々と出るため、回転率が高く収益が見込めます。
⑤レンタル事業
古物商許可を活用し、中古品のレンタルビジネスを行うことも可能です。
例を挙げるとすれば、
・レンタルビデオ
・レンタカー
・ブランド品や服のレンタル
など、同じ商品を繰り返し使用して収益を得る効率的なビジネスです。
ただし、レンタカー事業を行うには、道路運送法に基づく「自家用自動車有償貸渡業の許可」を別途取得する必要があります。
 レンタル業を始めるのに古物商許可以外に必要な資格はある?
レンタル業を始めるのに古物商許可以外に必要な資格はある?
![]()
レンタル業を始めるのに基本的には資格は必要ありません。
しかし、貸し出す商品によっては特定の資格や許可が必要になる場合があります。
【例外】資格が必要になるレンタル業
1.CDやDVDのレンタル業を始める場合、著作権を管理する団体からの許可が必要です。
2.レンタカー業を始めるには、自家用自動車有償貸渡業許可が必要です。
中古品のレンタル業を始めるには古物商許可が必要です。
これは中古品を仕入れて商売をするための資格であり、レンタル業にも適用されます。
ただし、新品を仕入れてレンタルする場合は古物商許可は不要です。レンタル業に古物商許可が必要かどうかは、レンタルする物を仕入れる段階で判断されます。
 お酒を買取り・販売する場合は古物商許可ではなく酒類販売業免許が必要?
お酒を買取り・販売する場合は古物商許可ではなく酒類販売業免許が必要?
![]()
お酒の売買にあたっては、古物商許可ではなく、販売先・販売形態に応じた酒類販売業免許が必要となります。
古物商許可を取得していてもお酒の販売はできません。古物商がお酒を販売するためには、別途「酒類販売業免許」などのお酒を提供するための免許や許可が必要となります。
 中古品の輸出・輸入には、古物商許可は必要?
中古品の輸出・輸入には、古物商許可は必要?
![]()
中古品を海外から輸入するとき、逆に海外へ輸出するとき、あらかじめ古物商許可の取得が必要ではないかと思われる方も多いと思います。
この点、輸出するのか輸入するのか、輸入するとして直接なのか間接なのかなどにより、要否が変わってきます。
1.海外で買い付けた中古品を日本国内で販売する場合
自ら海外へ直接に足を運んで、現地で買い付けた中古品を持ち帰るなどして日本国内で販売するという場合、古物商許可は受ける必要がありません。
2.日本国内の輸入業者が輸入した中古品を買取・販売する場合
日本国内の輸入業者が海外から輸入した中古品を、さらにその輸入業者から買い取ったり販売したりする場合、古物商許可を予め取得しておかなければなりません。
3.日本国内から、海外の業者に発注して中古品を輸入した場合
このパターンは、中古品を買い取る際に相手が外国の業者となるため、原則、古物商許可は不要と考えられます。もっとも、海外の業者から中古品を直接日本に仕入れる場合、管轄警察署によっては判断に迷われることもあります。
4.日本国内で買い取った中古品を海外へ輸出する場合
輸入とは逆に、日本国内で買い取った中古品を海外へ輸出する場合、古物商許可はもちろん必要です。買い取る時点で取引相手が日本国内に居るので、日本の法律が適用されるケースです。
 外国人が古物商許可を申請するときの注意点は?
外国人が古物商許可を申請するときの注意点は?
![]()
外国籍の人が日本国内で中古品の売買を行うときや、中古品を買い取って母国などに輸出する事業を始めるときは、あらかじめ営業所を設置する場所で古物商許可の申請・取得を行っておかなければなりません。
日本人と違いが生じるのは、主に次の2点です。
1.身分証明書の代わりとなる書面
外国人の方は日本国内に本籍地がありませんので、身分証明書(身元証明書)という本籍のある役所が発行してくれる「禁治産者や準禁治産者、破産者等ではない」ことを証明する書面が取得できません。
制度が変更になる前は、申請先の警察署によっては、身分証明書の代わりとなる書面の提出を求められることがありましたが、現在は、身分証明書の代わりとなる書面の提出は不要となりました。
2.古物商が可能な在留資格(ビザ)の種類
外国人が古物商許可の申請を行う場合や、日本在住の外国人が役員(または管理者)の会社で法人の古物商許可を申請する場合、在留資格に制限があります。
これは主に、古物「商」という商業的な行為を行うにあたって、その外国人が商行為を許された状態であることを確認するものです。
ケース・バイ・ケースで判断される傾向にあるため、「この在留資格だから許可が可能、この在留資格だから不可」と決めつけるのではなく、その外国人の諸状況によって個別に確認がなされます。
ご相談で多いのが、在留資格が「技術・人文知識・国際業務」の方が古物商許可を取得して営業を行えるかというご質問ですが、「技人国」では原則的には許可申請が難しいようです。
 古物商許可が下りるための条件(要件)は?
古物商許可が下りるための条件(要件)は?
![]()
古物商許可を受けるためには、以下の3つの要件を事前に確認しておきましょう。
これらの3つの要件を満たさない場合、許可を受けることができません。
1.主たる営業所を設けること
2.営業所ごとに常勤の管理者を置くこと
3.欠格事由に該当しないこと(申請者本人、法人役員、管理者)
 営業所が賃貸物件の場合、使用承諾書は必要?
営業所が賃貸物件の場合、使用承諾書は必要?
![]()
賃貸住宅を営業所とする場合に、基本的に使用承諾書の提出は求められません。
以前は使用承諾書が必須でしたが、現在の規定では提出義務がなくなったためです。
「使用承諾書が不要」とは、大家さんの承諾が不要という意味ではありませんのでご注意ください。
提出が不要なのはあくまで警察署への書類であり、営業所として利用する場合は、大家さんからの承諾をきちんと得ておくことが基本です。
賃貸契約書の使用目的も確認が必要です。通常、賃貸住宅の契約書には「居住用」と記載されています。居住用として契約した物件を無断で営業所に利用するのは規約違反となり、万一大家さんに知られた場合にはトラブルを引き起こす可能性がありますので、注意しましょう。
警察の公式ホームページに記載がなくても、申請書を提出する管轄警察署で使用承諾書の提出を求められるケースもあります。
 これから古物商の営業所を借ります。契約時のアドバイスは?
これから古物商の営業所を借ります。契約時のアドバイスは?
![]()
中古品売買の仕事をするために、これから営業所となる物件を借りるという場合は、
・賃貸借契約書の使用目的が「事務所」や「住居専用、ただし古物商の営業所としての使用は目的の範囲に含める」などの文言としてもらえるか
・使用目的欄を「住居専用」などから変更できない場合には、後日、古物商の営業所としての使用承諾書に賃貸人からの署名や押印をもらえるか
という点を確認しておくと安心です。
この使用承諾書ですが、「公営住宅」では住居専用として貸すことが前提となっているため、「古物商の営業所としての使用を承諾します」といった承諾は得られず、発行されないことが原則であり、公営住宅で古物商許可を取得することは、ほぼ不可能となるので注意が必要です。
未承諾の場合、最悪、賃貸借契約違反となってしまい退去を求められることも考えられます。
従って、賃貸人に古物商としての営業所として利用してもよいか、しっかり事前に確認を取ることが大切です。
 住民票の写しの記載事項について教えて
住民票の写しの記載事項について教えて
![]()
マイナンバーの記載なし・本籍地の記載ありのものが必要です。 ※発行後3か月以内のもの
住民票の請求先は住民登録している市区町村役場です。
 身分証明書とはなに?
身分証明書とはなに?
![]()
身分証明書というと運転免許証やマイナンバーカードをイメージする方が多いと思いますが、それらとは全く違う書類です。身分証明書とは次の事項を証明する書類のことです。
・禁治産・準禁治産の宣告を受けていない
・後見登記の通知を受けていない
・破産宣告の通知を受けていない
古物商許可の申請では、欠格事由に該当していないことを証明するため、身分証明書の提出が求められます。身分証明書は、本籍地の市区町村役場で取得できます。 ※発行後3か月以内のもの
 古物商許可のURLの届出とは?
古物商許可のURLの届出とは?
![]()
インターネット上で古物商取引を行う場合でも、古物商許可の申請が必要であり、尚且つ、インターネット上で古物商取引を行う場合には、許可申請の際に
・該当するURL
・その使用権限がある証明資料
が必要です。
URLの疏明資料はヤフオクのマイページを印刷して提出すればOKです。
ただし、下記の内容が必ず記載されていないといけません
①古物商許可申請時に提出する「営業所の名前」と一致する名称
②マイページのURL
メルカリのアカウントが商品ごとに分けてある場合や、メルカリの他に「Amazon」や「ヤフオク」などのショップサイトある場合には、すべてのURLとその疏明資料を提出する必要があります。
申請時点でホームページが未完成の場合には、ホームページが確認できず、調査が進められないため、届出は不要です。
ホームページが完成した後に、改めて変更届出を行いましょう。
 古物商営業に使用するホームページの届出手続きを詳しく教えて
古物商営業に使用するホームページの届出手続きを詳しく教えて
![]()
古物商に係る古物営業に関して、インターネットを利用して、電子メールや郵便等取引の相手方と対面しないで使用できる通信手段(非対面の方法)により古物の取引をしようとする場合には、公安委員会に届け出なければなりません。
【届出内容】
・12桁の許可証の番号(第○○○○○○○○○○○○号)
・許可年月日
・営業者の氏名又は名称
・当該ホームページのURL
※複数のURLのホームページを利用してホームページ利用取引をしている古物商についても、全てのURLについて届出を行わなければなりません。
【URLの届出が必要な場合】
次の場合はURLの届出が必要です。
・自社(自身)のホームページ(サイト)を立ち上げ、古物取引を行う
・ネットオークションサイトで個別のショップやストアを運営する
・「プロバイダ」や「サイト運営事業者」などから、「固有のURL」が割り当てられている
【URLの届出が不要な場合】
インターネットの利用はあっても、URLの届出が不要となることもあります。
主に次の場合です。
・オークションサイトで単品出品による販売
・情報や宣伝のみで、古物取引は行わない自社(自身)のホームページ
※「固有のURL」が割り当てられない場合や、自社(自身)のホームページは存在するが、古物に関する情報の記載がない場合などは、URLの届出は不要となります。
今後、自社のホームページなどで古物営業を行うことを検討している場合でも、現状ではホームページでの古物営業を行っていない場合は、URLの届出は不要です。ホームページ開設後に変更届出の手続きが必要となります。
【申請書の記載について】
申請用紙「(電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する方法を用いるかどうかの別)」の欄は、「用いる」を選択します。
送信元識別符号の欄にホームページのURLを記載します。
こちらの記載については、全てにふりがなを付ける必要はありません。しかしながら、誤読されやすい文字、数字の0(ゼロ)とアルファベットのO(オー)、数字の1(いち)とアルファベットのl(エル)などのように判別しにくい文字や誤読されやすい文字にはふりがなをつけて明確な記入をするよう注意しましょう。
【添付が必要とされるURLの使用権限疎明資料とは】
URLの届出をする場合、使用するURLについて、「申請者に使用権限があるか」、「URLのドメインは誰の登録か」を証明する必要があります。
その証明のために「登録者」、「ドメイン」、「発行元(プロバイダ)」などを確認できる書類の添付が必要であり、この証明書類を「URLの使用権限疎明資料」といいます。
具体的には、次のような資料です。
1.プロバイダ等が発行したドメイン割り当て通知書等
プロバイダ等から郵送・FAXが送付された書面の写し(ホームページのURLの割り当てを受けた際の通知書の写しなど) 書面には、「登録者名」「ドメイン(「http://www.○○○○jp」等の〇○○印の部分)」「発行元(プロバイダ)」の3点が通常記載されています。
2.WHOIS情報の検索結果をプリントしたもの
「WHOIS」とは、IPアドレスやドメインの登録者情報を誰もが参照できるサービスです。「WHOIS情報」とは、「レジストリ」、「レジストラ」によって提供されている、IPアドレスやドメインの登録者情報をいい、主に、以下の項目を参照することができます。・ 登録ドメイン名
・ レジストラ名
・ 登録ドメイン名のプライマリおよびセカンダリネームサーバ
・ ドメイン名の登録年月日
・ ドメイン名の有効期限
・ ドメイン名登録者の名前、住所
・ 担当者の名前、住所、電子メールアドレス、電話番号
情報が公開されていない場合は、正確なドメイン登録情報を参照することができませんので注意してください。
「ドメイン割り当て通知書等」、「WHOIS情報」で使用権限を証明することができない場合は、プロバイダやサイト運営事業者から、固有のURLに対する「使用承諾書」を取得することもできます。
プロバイダやサイト運営事業者によって、取得の方法も異なる場合がありますので、直接問合せをしてみましょう。
3.契約書の写しや証明書など
自身のものではなく、他人のホームページに相乗りする形で利用取引をしている場合などは、ホームページ利用に関してURLを使用する権限を付与されていることがわかる契約書の写しや、相手が発行した証明書などを提出します。
 法人の許可申請に必要な「登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」とは?
法人の許可申請に必要な「登記簿謄本(履歴事項全部証明書)」とは?
![]()
法人名義での申請の場合に必要です。
全国の法務局・支局・出張所で取得できます。
古物商許可申請に必要となる法人の登記簿謄本は、「履歴事項全部証明書」です。 ※発行後3か月以内のものが必要
取得方法には、①窓口での取得、②郵送での取得、③オンライン請求して窓口又は郵送で受け取る方法があります。
オンライン請求の詳細は、法務省ホームページ「登記事項証明書(会社・法人)を取得したい方」をご覧ください。
 法人の許可申請に必要な「定款」とは?
法人の許可申請に必要な「定款」とは?
![]()
法人名義での申請の場合に必要です。
現行の定款をコピーし、原本と相違ないことを証明する奥書を記載したものを準備しましょう。
奥書の方法は以下のとおりですが、念のため申請先の警察署にも奥書の方法を確認するようにしましょう。
【定款の奥書の作成方法】
1.コピーした現行定款の最終ページの余白に赤字で以下の文言を記載し、捺印する。
「以上、原本に相違ありません。
令和〇年〇月〇日
株式会社○○○○
代表取締役 ○○ ○○ 印」
※ 印は法人代表者印を捺印する(シャチハタ不可)
2.1を記載した定款のコピーを揃え、左端を2か所ホチキスでとめる。
3.各ページの綴じ目に割り印をする。
※ 割印は奥書と同じ法人代表者印を捺印する。
注意!
履歴事項全部証明書と定款の「目的」欄には、「古物営業を営む」ことが読み取れる記載が必要です。
そのような記載がない場合には、『速やかに事業目的に「古物営業を営む」ことが読み取れる文言を追加することを決定した』旨を記載した「確認書」の提出を求められる場合があります。申請先の警察署に確認しましょう。
また、法務局で事業目的の変更登記手続きを行う必要があります。
 取り扱う古物の品目の決め方は?
取り扱う古物の品目の決め方は?
![]()
古物商許可には有効期間がありませんので、つい「この品目も」「あの品目も取っておきたい」と考えてしまいがちですが、品目を多くすると、それぞれの品目について「すぐ取引の可能性があるのか」「真贋を見分ける目はあるのか」「経験はあるのか」と警察署で確認が入るケースが多いです。
そのため、古物商許可は「取引の可能性が高まったら」「必要な品目に限定して」申請するのがオススメです。
たとえば中古自動車はすぐ取り扱う予定があるけれども、古本はそのうち扱うこともあるかも、という理由で中古自動車と古書を取扱品目にしようとしても、予定が半年以上後であったりすると、「ではもう少し古物商としての営業が具体化したら、また来てくださいね」と断られてしまうこともあります。(古物営業法第6条の規定を参照)
 許可申請の窓口はどこ?
許可申請の窓口はどこ?
![]()
最寄りの警察署が必ずしも申請先とは限りません。
申請書類を提出するのは、当該主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。所轄の警察署がわからない場合は県警のHPで確認しましょう。
営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課です。
申請は原則、警察署に直接訪問してする必要があります。(郵送で対応する自治体もある)
 申請手数料とはなに? 注意点は?
申請手数料とはなに? 注意点は?
![]() 申請手数料とは、警察署で申請書類が受領された時に支払うもので、金額は19,000円です。
申請手数料とは、警察署で申請書類が受領された時に支払うもので、金額は19,000円です。
支払方法は、都道府県によって現金・都道府県の収入証紙の購入・キャッシュレス決済等の違いがあります。あらかじめ確認が必要です。
申請を取り下げた場合や、申請の結果が不許可だった場合でも返金されませんのでご注意ください。
 申請手数料はどのように納める?
申請手数料はどのように納める?
![]()
申請手数料は現金で納付するわけではありません。
証紙を購入することで納入します。
間違いやすいの点なのですが、収入印紙ではなく、県証紙で納めます。
間違って、収入印紙を買って持っていくということがないようにしましょう。
とは言っても、この件証紙は申請先の警察署内で購入できるものですので、当日支払えるだけの現金を持っていけば何も問題ありません。
また、県証紙を買う前に担当の方に書類をチェックしてもらうようにしましょう。
申請した結果、古物商許可が必要ないケースに該当してしまった場合、許可不要になるため、無駄に県証紙を購入してしまうことになってしまいます。
 申請書提出の際の面談で注意することは?
申請書提出の際の面談で注意することは?
![]()
申請書を提出する際には、古物商の担当者と面談する場合があります。
この面談では、営業所や取り扱い商品、仕入れや販売方法などに関する情報を聞かれることがあります。
面談でのやり取りは、申請を受理するかどうかの判断材料となります。
また、新規でHPを登録する場合には、面談中に対象URLにアクセスして内容を確認することもありますので、その点にもご注意ください。
 古物台帳とはなに? いつまでに準備が必要?
古物台帳とはなに? いつまでに準備が必要?
![]()
古物台帳とは、古物商が古物の取引を記録する帳簿です。「帳簿等の保存義務」に基づいて作成・保管が義務付けられており、盗品などの流通を防ぎ、取引の透明性を確保する役割があります。
古物台帳は、ノートやパソコンなどを使用して記録することができます。原則として1万円以上の取引は必ず記録し、3年間保管する必要があります。
1万円以下の取引で、自動二輪車や原動機付自転車、家庭用テレビゲームソフト、CD・DVD、書籍などの例外品を除く場合は記録は不要です。
管轄警察署による現地確認までに古物台帳を準備しましょう。
 管轄警察署による営業所の現地確認はある?
管轄警察署による営業所の現地確認はある?
![]()
古物商許可の取得するまでは、申請してから約40日程度かかります。
申請時に管轄警察署の担当者に口頭で確認を受けるのが一般的ですが、都道府県や管轄警察署、または申請内容によっては、標準処理期間の間に営業所の立入調査が行われる場合もあります。
その際、営業所が実在するかどうか、中古車の売買をするのであれば、駐車場があるかどうかなどの確認が行われます。その他に営業所が独立したスペースになっているのか、商品を置く棚やスペースが確保されているのか、古物台帳は準備できているのか、月々の物品の取り扱い量はどれくらいか、などチェックされる場合があります。
【確認されるポイント】
1.営業所について
・実在しないバーチャルオフィスなどではないか(営業所が実在するかどうか)
・どのように古物取引をするのか
・中古車の売買をするのであれば、駐車場があるかどうか
2.古物の種類について
・古物取引をするための環境が整っているかどうか(営業所・保管場所が独立したスペースになっているか)
・取引する古物の保管場所はあるか
3.管理者について
・取り扱う古物について専門性や知識があるかどうか
・月々の物品の取り扱い量はどれくらいか
・古物台帳は準備できているのか
 古物商許可証の有効期間は?
古物商許可証の有効期間は?
![]()
物商許可証の有効期間はどれくらい?というご質問は、これから許可を取得される方からよく聞かれることがあります。
回答としては、「古物商許可証には有効期間がない」ということになりますが、変更手続きを失念してしまい取消になるケースもあります。
古物営業法第6条の規定により、管轄警察署によって判断に差があるものの、6ヶ月以上営業しない場合には古物商許可証を返納してくださいという運用がとられます。
営業所の場所が変わった場合などの変更届は、別途必要になることがあります。
 従業員が許可証を持っていれば会社で古物商が可能?
従業員が許可証を持っていれば会社で古物商が可能?
![]()
古物商許可に関して多いご質問として、「会社の社員(従業員)が古物商許可証を持っているから、会社として中古品の売買をしても合法でしょ?」というものがあります。
個人と会社(法人)の古物商許可は全くの別物です。
結論から述べると、会社の従業員や役員(たとえ社長であっても)が古物商許可を取得していたとしても、会社自体が中古品の売買事業を行うことはできません。理由は、個人の許可と会社の許可は、全く別の扱いとなっているからです。
ちなみに、ここでいう「個人の古物商許可」とは、個人として(個人事業として)中古品の売買を業とする場合に必要となる許可のことです。自分一人で、あるいは個人事業主として従業員を雇いながら古物商を行うときは、この個人の古物商許可が必要です。
一方「法人の古物商許可」とは、会社として(会社の名前と所在地で)中古品の売買を業とする場合に必要となる許可のことです。
それでは、「中古品を社員名義で買い取って、それを会社で販売すれば問題ないのでは?」というご質問になるわけですが、これも結論としては「不可」となります。
なぜなら、仮に中古品を買い取るのが社員個人だとしても、その社員が買い取った商品を会社がさらに買い取るのであれば、その時点で結局は会社に古物商許可が必要となってしまうからです。
 古物商許可を個人から法人へ切り替える方法は?
古物商許可を個人から法人へ切り替える方法は?
![]()
古物商許可においては、個人で古物商を行う場合は個人の許可が、また会社として古物商を行う場合は法人の許可が、それぞれ必要となります。
【法人の古物商許可を取り直すのが原則】
結論としては、個人として受けていた古物商許可を返納し、新たに法人(会社)として古物商許可を取り直すことになります。
では、個人として(個人事業で)中古品の売買を行っていた人が、途中で会社を作って法人化したとき、古物商許可はどうしたらよいのでしょうか。
もっとも、この原則通りの手続きだと、個人としての古物商許可を返納して新たな法人の許可を取得するまでにタイムラグが生じ、その間営業ができないことになってしまいます。(営業所の管理者も複数許可を兼ねることができないので、個人で管理者になっている場合には法人の管理者にはなれないことになります)
そこで、実際の古物商許可行政においては、既に古物商許可を個人として受けて営業している人に対しては、法人(会社)の古物商許可証が発行されると同時に個人の古物商許可証を返納するということを条件に、先に法人の許可申請を受理してくれるという運用がなされていることが多いです。
この点、管轄警察署などによって手続きの流れが異なる場合がありますので、法人(会社)の許可へ切り替える予定の方は、早めに相談しておくとよいでしょう。
 中古自動車の販売会社を設立するには?
中古自動車の販売会社を設立するには?
![]()
中古品を取り扱う事業の中でも、とりわけ中古車の販売を始める場合は、最初から法人化(会社設立)して事業を開始されることが多いと思います。最近では、日本国内で中古車を仕入れて諸外国へ販売する事業を始めるために、まずは会社設立を予定される方も増えています。
当事務所では、司法書士事務所と連携することで、中古車の販売を行う会社を設立し、中古品売買に必要となる古物商許可と、廃車の引取に必要な自動車引取業の登録まで、トータルにサポート・代行するサービスをご用意しております。
ただし、会社設立後に古物商許可と自動車引取業登録を行う前提でご案内しておりますが、廃車の引取を行わない業態の場合は、自動車引取業登録の手続きは不要です。
中古自動車販売の会社を株式会社として設立予定の方、または合同会社として設立予定の方、当事務所は司法書士事務所と連携して、どちらにも対応、設立手続きをトータルにサポートいたします。
会社設立後に必要となる、警察署への古物商許可の申請と行政庁への自動車引取業登録において求められる、事業目的の記載なども定款作成時に反映しますのでご安心ください。
 古物商許可を取得後、URLを取得・変更したので届出手続きをサポートしてもらえないか?
古物商許可を取得後、URLを取得・変更したので届出手続きをサポートしてもらえないか?
![]()
当事務所では、山梨県で許可を取得されている古物商許可業者様を中心に、インターネット上で古物を取扱う際に必要となるURLの届出手続きの代行サービスを提供中です。
・届出手続きの方法がわからない
・平日の昼間に警察署へ出向くことが難しい
・行政手続きは専門家に任せて、事業活動に専念したい
・届出手続きで失敗したくない
などの理由でお悩みでしたら、当事務所にお問い合わせください。
届出費用
33,000円(税込)~ ※URL追加2件目以降、1件につきオプションとして+2,200円必要。
※郵送費や交通費などの実費は別途申し受けます。
ご準備頂きたい資料:
古物営業で使用されたいホームページのURLが、事業者さんが使用権原を有していることがわかる資料をご準備ください。
例えば、プロバイダーから発行されたドメイン割り当て通知書や、WHOIS情報の検索結果を印刷したものが使用権原を有していることがわかる資料に該当します。
 会社設立も一緒にお願いできないか?
会社設立も一緒にお願いできないか?
![]()
当事務所では古物商許可と並行しての会社設立手続きも承ることが可能ですので、もし個人事業ではなく会社として中古品売買を行うご予定の場合は、会社設立+法人の古物商許可も申請代行を承っております。
 許可取得後に必要な義務を教えて
許可取得後に必要な義務を教えて
![]()
古物商取引の防犯三大義務
1.取引相手の確認義務
2.不正品の申告義務
3.帳簿等への記録義務
許可を取得しても無制限に営業できるわけではなく、古物商として法律で定められた三大義務を守りながら営業する必要があります。
これらは防犯三大義務と呼ばれていますが、これらは盗品等の流通を防止することで犯罪を防止し、被害を迅速に回復するために必要と言われています。
取得後に立入検査がある理由は、古物商取引の防犯三大義務を怠っていないか確認するためです。

運営事務所について

ソシエプラス社会保険労務士事務所 代表 三枝 進
はじめまして、当事務所の代表を務める 三枝 進(さえぐさ すすむ)と申します。
弊所は古物商をはじめとした各種許認可申請、会社設立、助成金や補助金、外国人の在留ビザ、社会保険関係の手続きなど幅広く実績多数です。
明るく、元気に、いきいきと働ける環境を整えることこそが、良い仕事と良い社会を生み出す基盤であると私は信じています。
そのために、企業や経営者の皆さまに寄り添い、働きやすい社会の実現に向けた環境づくりをサポートすることが、私の使命だと考えています。
ご依頼に対しては、スピーティーかつ全力で取り組むことを心掛けております。ぜひ、みなさまのお問合せをお待ちしております。
| 運営事務所 ソシエプラス社会保険労務士・行政書士事務所 |
| 事務所所在地 〒400-0835 山梨県甲府市下鍛冶屋町69-20 |
| 営業時間 平日9:00~18:00 ※祝祭日除く |
| 電話番号 055-215-4621 |
| Mail info@socieplus.com |
| 所属登録番号 行政書士登録番号:25163201 社労士登録番号:19250003 |
| 適格請求書発行事業者 登録番号:T1810154563684 |
| 取扱業務 古物商など各種許認可申請、会社設立、助成金・補助金、外国人在留ビザ、社会保険手続きなど |
| 運営サイト https://socieplus.com/ |
全国の行政書士様、山梨県の古物商許可申請の提出代行承ります!
古物商許可申請を全国で行っている行政書士様、山梨県の提出代行についても承っておりますのでお問い合わせ願います。すでに実績がございますのでご安心願います。弊所は適格請求書発行事業者です(T1810154563684)。
古物商許可が必要かどうかの質問もお気軽にお問い合わせください
個人のお客様で副業でせどり等を行っているお客様、是非一度ご確認願います。
以上が個人の古物商許可の申請代行に関するご案内です。