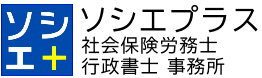社会保険労務士 業務について
- 社会保険労務士(社労士)は、どんな仕事をするんですか?
-
社会保険労務士とは、
労働・社会保険に関する法令の専門家として、企業の採用から退職までの「人」に関する専門知識を活かし、人事・労務管理のコンサルティング、各種書類の作成代行・提出代行、年金に関する相談などを行う国家資格者です。
企業とそこで働く労働者の双方の福祉向上と、企業の健全な発展を支援する役割を担います。業務の一例:
・労働・社会保険手続き代行:入社・退職時の手続き、保険料計算など。
・給与計算代行:毎月の給与計算、年末調整。
・就業規則の作成・変更:会社のルールブック作成。
・労務相談・コンサルティング:採用、人事評価、ハラスメント対策など。
・助成金の申請代行:雇用関連の助成金活用支援。
・年金相談:老齢・障害・遺族年金の手続きサポート。
これらの専門知識で、企業の人事・労務管理を幅広く支援します。
- 手続き業務は自社でしていますが、労務相談のみ顧問契約もできますか?
-
対応しております。お気軽にご相談ください。
労務に関する相談のみの対応もお受けしております。
ハラスメント相談、労働時間・休暇に関する相談、メンタルヘルスに関する相談、待遇をめぐる問題に関する相談、労災に関する相談はもちろんですが、採用や教育などの相談も対応しております。
製造業やサービス業の分野でも実務経験が豊富です。ぜひ一度ご相談ください。 - 給与計算のみお願いしても良いですか?
-
給与計算と社会保険手続きをセットでお受けしております
当事務所では、法律に準拠した正確な給与計算を通じて、企業の皆様をサポートしています。
未払い残業のリスクをなくす
「給与計算は誰がやっても同じ」と思われがちですが、労働関係法令は非常に複雑です。当事務所の経験から、企業の約8割で給与計算に間違いが見受けられます。 特に、見過ごされがちなのが「未払い残業」です。これは企業にとって「見えない負債」となり、大きなリスクを抱えることになります。私たちは、社会保険労務士が法律に基づいて正確な計算を行うことで、このリスクを最小限に抑えます。
従業員の方が安心して働ける環境を整えることは、企業の信頼向上にもつながります。ミスのない給与計算と社会保険手続きの連携
給与計算のミスは、社会保険手続きとの連携不足が原因で起こることも少なくありません。当事務所では、より正確な給与計算を提供するため、給与計算代行と社会保険手続きをセットで承っております。
これにより、情報連携のミスを防ぎ、正確性を高めることができます。セットでのご依頼となりますが、料金はリーズナブルに設定しておりますので、ご安心ください。まずはお気軽にご相談ください。
- 給与計算は自社で行いますので、社会保険手続きをお願いします。
-
対応可能です。
当事務所の顧問契約は、社会保険手続きの代行に加えて、企業の皆様の経営に深く関わる「労務全般の相談」にも対応しています。
主な特徴
経営の身近なパートナー:
社会保険手続きだけでなく、日々の労務に関するご相談に幅広く対応し、経営をサポートします。追加料金なし:
月額料金には日常的に発生する業務がほとんど含まれているため、費用が見通しやすく、安心してご利用いただけます。スムーズな連携:
ITツールの活用により、お客様との連携をよりスムーズに行うことができます。ぜひ、他社と比べてご検討ください。
契約・費用について
- サービス内容を詳しく知りたいのですが、相談は無料ですか?
-
初回無料相談を承っております。
社労士事務所の業務範囲やサービス内容は、事務所によって大きく異なります。
当事務所では、初回無料相談にてサービス内容や進め方について詳しくご説明しております。 - 顧問契約の費用はいくら位かかるのでしょうか?
-
当事務所では、顧問契約のサービス内容と従業員数に応じてわかりやすいプランを用意しております。
サービス内容について
当事務所では、まずお客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適なプランをご提案いたします。主なサービス内容
・給与計算・社会保険手続きのアウトソーシング・労働保険分野のサポート(健康診断結果の医師の意見聴取、メンタルヘルスなど)
・業務のデジタル化・内製化支援(社会保険手続き、給与計算、ペーパーレス化など)
費用について
顧問料は 月額 16,500円(税込)からお承りしています。詳細については、当事務所ウェブサイトの
「契約形態・報酬」ページにてご確認いただけます。 - 追加費用は掛かりませんか?
-
お客様にご納得いただいていない費用は発生いたしませんのでご安心ください。
顧問料のほかに追加料金が必要な際は、都度ご説明させていただきます。
お客様が知らないうちに費用が増えるようなことはございませんのでご安心ください。当事務所では分かりやすい料金体系を心掛けております
行政書士 業務について
- 行政書士と司法書士の違いと業務内容を教えてくだい
-
行政書士と司法書士の違いと、行政書士の業務を説明します。
行政書士は、官公署へ提出する許認可等の書類作成や手続きの代理、権利義務・事実証明に関する書類の作成を専門とします。一方、司法書士は、法務局に提出する不動産登記や会社設立などの登記手続きを専門とします。
つまり、行政書士は行政手続きの専門家、司法書士は登記手続きの専門家という違いがあります。業務範囲は異なりますが、会社設立のように両者の専門分野が関連するケースもあります。
また、行政書士の主な業務内容は以下の通りです。
官公署に提出する書類の作成:
建設業許可や飲食店営業許可、風俗営業許可など、事業に必要な各種許認可の申請書類を作成し、提出を代行します。権利義務に関する書類の作成:
遺産分割協議書、契約書、示談書、内容証明などの作成をサポートします。事実証明に関する書類の作成:
財務諸表、会計帳簿、実地調査に基づく図面類などの作成を行います。外国人関連業務:
在留資格の申請、永住許可、帰化申請など、外国人の日本での生活・就労に関する手続きを支援します。 - 相談料はいくらですか?
-
1回 税込5,500円(1時間程度)です。
正式に手続業務をご依頼いただいた場合、お支払いいただいた相談料は報酬額に充当いたしますので、この場合は実質的に相談料無料になります。
なお、営業時間外のご相談は、1回 税込8,250円(1時間程度)を申し受けます。 - 手続を依頼するのにどれくらいの費用がかかるが心配です。
見積りを事前に教えてもらうことはできますか? -
相談予約の時点で、一般的な費用の目安をお伝えすることは可能です。
実際の費用はお客様の状況によって異なりますので、面談にてくわしくご事情をお聞きし、お見積りいたします。
お見積りにご納得いただけなければ、依頼される必要はございません。 - 相談のときの持ちものを教えてください。
-
以下のものをお持ちください。
1.関連する書類(状況がわかる資料など)
必須ではありませんが、お持ちいただいた方がご相談がスムーズです。
2.身分証明書(運転免許証、在留カード、パスポートなど) 原本
本人確認をさせていただきます。
3.印鑑(シャチハタ印以外)
ご相談後、そのまま弊所に依頼される場合は、引き続き業務委任契約の締結をさせていただきます。
ご相談のみの場合は不要です。 - どのタイミングで相談するのがよいですか?
-
早ければ早い方がよいです。
ご相談のタイミングによっては、手遅れになったり、余分な費用や時間を要したりすることがあります。
ご自身で手続を予定されている場合であっても、できる限り早い段階で専門家の診断やアドバイスを受け、正しい情報や知識を得ることをおすすめします。 - 行政書士に相談すべきことかどうかわかりません。
どこに相談したらよいかわかりません。 -
行政書士に相談できる内容かわからない・相談先がわからないという場合も、当事務所にお気軽にお問い合わせください。
行政書士で対応できない分野の場合は、他の専門家や機関をご案内・ご紹介いたします。
その場合、ご紹介料をいただくことはございません。
業務について
- 必ず受任してもらえますか?
-
お客様のご事情をくわしく伺い、弊所で対応することが難しいと判断した場合には、受任することができかねる場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 依頼したらすぐに業務をスタートしてもらえますか?
-
業務委任契約書にご署名・ご押印をいただき、着手金の入金確認ができましたら、業務に着手いたします。
- 費用はいくらくらいかかりますか?
-
ご依頼の内容やお客様の状況によって費用は異なります。
ご相談時にご事情を伺い、お見積りをいたします。
概算金額は事業所についての費用・報酬のページでご覧いただけます。 - 費用にはどのようなものがありますか?
いつ支払えばよいですか? -
お支払いいただく費用とお支払い時期は以下のとおりです。
業務の種類によっては、業務依頼時に一括払い(報酬の100%)をお願いすることもあります。
着手金(報酬の50%)
業務依頼時にお支払いいただきます。
着手金をお支払いいただいた時点から業務に着手しますので、途中で依頼をキャンセルされた場合でも返金いたしかねます。
また、手続の結果が不許可になった場合などお客様の目的が達成されなかった場合でも、返金いたしかねます。
成功報酬(報酬の50%)
業務終了時にお支払いいただきます。
手続の結果が不許可になった場合には、お支払いいただく必要はありません。
実費
事前に判明しているものは業務依頼時に、業務着手後に新たに発生したものは業務終了時に、お支払いいただきます。
・郵送料
・官公署におさめる申請手数料・収入印紙代
・公的証明書(住民票、納税証明書など)の発行手数料
など - 費用の支払い方法を教えてください。
-
以下をご利用いただけます。
1.現金
2.銀行振込 ※手数料はお客様にてご負担くださいますようお願い申し上げます。 - 提出した書類のコピーはもらえますか?
書類の保管をお願いできますか? -
重要な資料の原本をお預かりする際は、お預かり証とコピーをお渡しいたします。
官公署に提出する書類一式はコピーし、ファイリングして業務終了時にお渡しいたします。また、弊所で承った業務につきましては、厳重なセキュリティのもと書類を保管させていただいております。
- 依頼を途中でキャンセルすることはできますか?
-
お客様のご都合により、いつでもキャンセル可能です。
ただし、着手金は返金いたしかねます。
また、すでに実費が発生している場合には、お支払いいただきます。
その他 共通
- 遠隔地であっても対応は可能ですか?
-
対応可能です。オンラインで全国に対応しております。
スムーズなコミュニケーションと効率的な手続き
当事務所では、お客様との連絡にChatworkとZoomやGoogle Meetを活用し、スピーディな対応を心がけています。Chatwork:ちょっとしたご質問や確認に便利です。
Zoom、Google Meet:より複雑なご相談や、顔を見ながら話したいときに最適です。
ご相談内容に合わせて使い分けることで、効率的に課題を解決できます。
また、各種申請業務にはクラウド管理システムや電子申請システムを導入しており、スムーズに手続きを完了させることが可能です。これにより、お客様の業務効率化にも貢献します。
- 弁護士、税理士、司法書士など専門家をご紹介していただけますか?
-
もちろん大丈夫です。
同じ士業でもそれぞれ専門(得意)分野が分かれることはよくあります。
当事務所の豊富なネットワークから、御社に最も適切な専門家をご紹介させていただきます。
- 提携先は、募集していますか?
-
長期的な視点で、良好な関係を築ける提携先を求めています。
顧問先のために一緒に成長できるプロフェッショナルを常に募集しています。
ご連絡をお待ちしております。